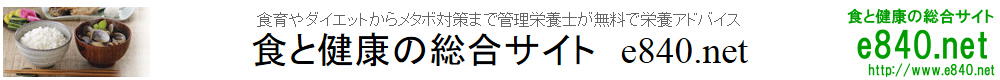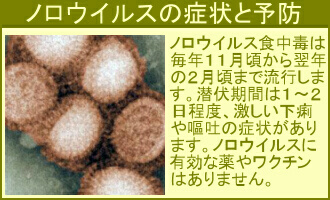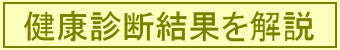γ-GTPの基準値
| 生化学血液検査項目 | 基準値(参考値) | |||
| 生化学血液検査名称 | 略称 | 数値 | 単位 | |
| γ-Glutamyltranspeptidase | γ-GTP | 50未満 | IU/L | |
γ-GTP検査の目的
γ-GTP血液検査は、一般的な血液検査になります。γ-GTP血液検査は、肝機能が正常に働いているかを検査しています。肝臓は、心臓の体循環システムの中で肝動脈と門脈から栄養の供給を受けながら体内の成分調整やアルコールの分解など非常に多くの機能を担っている重要な臓器です。 しかし、この肝臓の最大の特徴には肝機能障害などが発症しても初期段階においては自覚症状がほとんど現れないという特徴があります。この特徴が「肝臓は沈黙の臓器」と呼ばれる由縁でもあります。 この沈黙の臓器である肝臓の病気を発見できる多くのケースは健康診断などの定期検診などです。 今まで特に自覚症状もなく自分は健康であると思っていた方が健康診断などの検査によってガンマGTP数値が上昇していることを発見するようなケースが大半です。
γ-GTP血液検査結果で何を調べているのか
肝胆道の疾患時には、γ-GTPのほかにALPやLAPも同じように値が上昇します。特にγ-GTPは、アルコールの常飲で大幅に高い値を示します。また、γ-GTPは血清のみならず、尿,胆汁、唾液、羊水などでも検出可能であるが、血清のγ-GTPは、主として肝・胆道系の疾患を特異的に反映すると考えられています。肝臓のγ-GTPは肝細胞のマイクロソーム分画や細胆管などに存在し、ALP、LAPなどとともに胆道系酵素とも呼ばれています。一方肝細胞癌に特異的なγ-GTPは、活性値の増加からは判断できず,アイソザイム分画によって泳動の異常バンドとして認められています。また、胆汁うっ滞では,γ-GTPの合成誘導と胆汁への排泄障害の結果,血清γ-GTP値が上昇します。一方,アルコール性肝障害や薬剤性肝障害での上昇は、合成の誘導に起因しています。
γ-GTPの検査結果からわかる病気
γ-GTPが血液中に多くなっても、それ自体が何か悪い影響をおよぼすことはありません。γ-GTPが高くなる疾患には、肝臓の細胞が破壊される肝炎、肝臓に脂肪が蓄積する脂肪肝などがあり、胆石や胆道癌などで胆道がつまった場合にもγ-GTPが高くなります。また、健康診断のときに注意して見なければいけないのが、アルコールによる肝脂肪です。特にアルコールを飲む中年男性の場合、飲みすぎによるアルコール性脂肪肝が問題になります。γ-GTPの正常値は男性で50国際単位(IU)以下、女性で32国際単位(IU)以下です。γ-GTPの値が100以下であれば、節酒あるいは禁酒することですぎに正常値にもどります。γ-GTPは比較的アルコールに短期間に反応するので、飲酒を一週間もやめればγ-GTPの値は下がりだします。
| 検査結果 | 考えられる原因と疾患の名称 | |||||||||||||
| 基準値より高値 | 肝外胆管閉塞、肝内胆汁うっ帯、薬物性肝障害、慢性肝炎、胆管細胞がん、脂肪肝、急性肝炎、肝硬変、アルコール性肝障害、肝細胞がん | |||||||||||||
| 基準値より低値 | 妊娠時の胆汁うっ滞性黄疸、先天性低γ-GTP血症、高グルタチオン尿症、高グルタチオン血症 | |||||||||||||
| 【備考】 γ-GTP血液検査結果が適正範囲より大きく乖離している場合には疾患の可能性があります。また、γ-GTPの血液検査結果によって、疑われる疾患を下表にまとめてみました。
γ-GTP:γグルタミルトランスペプチダーゼ 単位:IU/リットル(γ-GTPの量を1リットル中の国際単位で示したものです) 【関連項目】 総ビリルビン、直接型ビリルビン、総たんぱく、アルブミン、コリンエステラーゼ、チモール混濁試験、硫酸亜鉛混濁試験、AST(GOT) ALT(GPT)、γ-GTP、アルカリフォスファターゼ、ロイシンアミノペプチターゼ、乳酸脱水素酵素、インドシアニン・グリーン、アンモニア、総コレステロール、B型肝炎ウイルス表面蛋白抗原、C型肝炎ウイルス核酸定性、C型肝炎ウイルス核酸定量 クレアチンキナーゼ、脳性ナトリウム利尿ペプチド、ミオグロビン、心筋トロポニンT |
||||||||||||||
γ-GTP値が100を超えたら病院に行きましょう
γ-GTP値が100を超えた時は、注意が必要です。特にγ-GTPの値が100~200になりますと脂肪肝が進行している可能性があります。γ-GTP値は、飲酒との関係が強く日頃からアルコールの摂取量が多い方は、病的状態になっているおそれがあります。また、γ-GTP値が200以上になった場合は、アルコールだけでなく、胆石や胆道がんなどによって胆道がつまっている可能性があるので精密検査を受ける事をおすすめします。さらにγ-GTP値が500以上になる場合はほとんどありませんが、胆道が詰まり胆汁が十分に分泌されてない場合にはγ-GTPの値が500を超える事もありますが、黄疸など他の症状も確認する事ができます。また、アルコールが原因でγ-GTP値が500以上になる場合もあります。しかし、γ-GTPが500を超える状態ですと大量の飲酒、あるいは急性アルコール中毒といったきわめて危険な状態にあります。γ-GTPは、アルコール摂取で上昇する血液検査である事を十分に理解したうえで、もしγ-GTP値が100をこえたら節酒(禁酒)をおすすめします。また、飲酒以外の原因があるかもしれませんので、心配な方は、病院に行く事をおすすめします。もし、γ-GTPの値が200以上になったら必ず病院に行き精密検査を受けましょう。
γ-GTP値が高い時に行う病院での検査
γ-GTP値が高い方は、必ず病院に行き、医師による診察を受けましょう。病院では、肝臓に関係したほかの逸脱酵素(GOT、GPT、ALPなど)に加え、黄疸の有無を調べることになります。また、腹部エコー検査も実施をし、γ-GTP値が上昇した原因を調べます。また、γ-GTP値が高い患者さんは、肥満体型である事がおおいので、コレステロールや血中脂質なども測ります。脂肪肝によるγ-GTP値の上昇であれば、、お酒をやめるという方法に加え、カロリーをとりすぎないためのダイエット療法を行います。また、コレステロールが高い場合には、薬物治療を同時に開始することがあります。もちろん胆石や胆管がんがあれば、検査と治療を行います。γ-GTPの上昇がみられたら生活習慣の改善が必要です。
その他の健康診断の検査一覧
| 血液検査項目 | 血液検査結果からわかること | ||
| 肥満度 | 肥満度(BMI)とは、体重と身長の関係から算出される、ヒトの肥満度を表す体格指数です。 | ||
| 血圧 | 脳卒中や心筋梗塞などの原因となる高血圧や、低血圧などを判定。測定値は、日によって、また時間によって変動するので、何回か測ることが必要。 | ||
| 血 清 脂 質 検 査 |
T-Cho | 数値が高いと動脈硬化の原因となり、心筋梗塞や脳梗塞などの病気を誘発してしまう。脂や脂肪分を多くとりがちな食生活の欧米化の影響で、高い人が増加しています。 | |
| HDL-C | 血管内に付着する脂肪分を取り除き、動脈効果を防ぐことから「善玉コレステロール」と言われています。低いと心筋梗塞や脳梗塞などの病気を誘発してしまいます。 | ||
| LDL-C | 比重の低いリポ蛋白コレステロール。いわゆる悪玉のコレステロール。 | ||
| 中性脂肪 | 体内の脂肪の主な成分でエネルギーとして利用され、余った分は皮下脂肪や内臓脂肪として蓄えられます。肥満、食べ過ぎ、飲みすぎで上昇し、動脈硬化や脂肪肝の原因になります。 | ||
| 貧 血 な ど |
赤血球数 | 血液中の赤血球数を調べ、低いと貧血が疑われます。生理出血の増加や、鉄分が不足している場合も低くなることがあります。 | |
| ヘモグロビン | 赤血球の成分のひとつで、主に血液中の酸素を運搬する役割を果しています。 | ||
| ヘマトクリット | 血液中の赤血球の容積の割合(%)を表し、低い場合は貧血の疑いがあります。 | ||
| 白血球数 | 白血球は、外部から進入した病原体を攻撃する細胞で、高いと感染症や白血病、がんなどが疑われます。外傷がある場合や喫煙、ストレス、風邪などでも上昇します。 | ||
| 腎 機 能 |
尿 検 査 |
尿たんぱく | 尿中に排泄されるたんぱくを調べ、腎臓病などの判定に用います。激しい運動の後、過労状態のとき、発熱時などに高くなることもあります。 |
| 尿潜血 | 尿中に血液が出ていないか調べます。陽性の場合、腎臓病や尿路系の炎症が疑われます。 | ||
| 血液 | クレアチニン | 筋肉内の物質からつくられ、尿から排泄されるクレアチニンの量を測り、腎臓の排泄能力をチェックします。高い場合、腎機能障害や腎不全が疑われます。 |
|
| 痛風 検査 |
尿酸 | 尿酸は、細胞の核の成分であるプリン体が分解してできた老廃物です。代謝異常により濃度が高くなると、一部が結晶化し、それが関節にたまると痛風になります。 | |
| 肝 機 能 検 査 |
ZTT | 血清に試薬を加えると混濁する反応を利用して、血液の濁りぐあいを測定します。濁りが強いと数値は高くなり、慢性肝炎や肝硬変が疑われます。 | |
| 血清酵素 | GOT | GOTとGPTはともに肝臓に多く含まれるアミノ酸を作る酵素で、肝細胞が破壊されると血液中に漏れ、数値は高くなります。肝炎や脂肪肝、肝臓がんなど、主に肝臓病を発見する手ががりとなります。 | |
| GPT | |||
| γーGTP | アルコールに敏感に反応し、アルコール性肝障害を調べる指標となっています。 | ||
| ALP | 肝臓、骨、腸、腎臓など多くの臓器に含まれている酵素で、臓器に障害があると血液中に流れ出ます。主に胆道の病気を調べる指標となります。 | ||
| 総たんぱく | 血清中のたんぱく質の総量。高い場合は、慢性肝炎や肝硬変など、低い場合は、栄養不良や重い肝臓病が疑われます。 | ||
| 総ビリルビン | ヘモグロビンから作られる色素で、胆汁の成分になっています。黄疸になると体が黄色くなるのはビリルビン色素が増加するためです。 | ||
| 糖 尿 病 |
尿糖 | 尿の中に糖が出ているかを調べ、糖尿病を見つける指標のひとつとされています。陽性の場合は、糖尿病や膵炎、甲状腺の機能障害などの疑いがあります。 |
|
| 空腹時血糖 | 空腹時の血液中のブドウ糖の数値(血糖値)を調べ、糖尿病をチェックします。糖尿病の疑いがある場合は、ブドウ糖付加試験を行います。 | ||
| HbA1c | 血糖検査では、血液を採取したときの値しかわかりませんが、HbA1cは120日以上血液中にあるため、長時間にわたる血糖の状態を調べることができます。糖尿病の確定診断の指標に用いられたりします。 | ||
| 便潜血反応 | 大腸や肛門からの出血に反応し、陽性の場合、大腸のがんやポリープが疑われます。 | ||